
コーア・クリント
Kaare Klint
コーア・クリントはコペンハーゲンで育ち、幼少期に絵画を学んだ後、15歳から父の建築事務所で建築を修めました。1914年に人体寸法に基づくFaaborg Chairを発表し、軽量かつ高い耐久性を両立する機能美で注目を集めました。1924年に王立芸術アカデミーに家具科を創設し、精密な測寸学と伝統様式の再構築(リデザイン)を教育に取り入れました。デザイナーと職人の協働を重視し、ボーエ・モーエンセンやオーレ・ヴァンシャーらを育成。これが1950年代のデンマーク家具黄金期と呼ばれる国際的評価の基礎を築き、“モダンデザインの父”と称される所以です。

アルネ・ヤコブセン
Arne Jacobsen
アルネ・ヤコブセンはコペンハーゲン芸術学院で学び、設計コンペで連戦連勝を重ねた建築家兼デザイナーです。1952年のAnt Chair、1955年のSeven Chairは成形合板技術で椅子の軽量化と量産性を飛躍的に向上させました。1958年にはSASロイヤルホテルで建築、家具、照明、カトラリーを統一したデザインを手掛け、空間全体を一つの芸術作品とする“総合芸術”を体現しています。細部への徹底したこだわりと完璧主義的プロポーション感覚は、現代にも大きな影響を与え続けています。

フィン・ユール
Finn Juhl
フィン・ユールはコペンハーゲン芸術アカデミーで建築を学んだ後、家具に彫刻的表現を導入した先駆者です。ヘンリー・ムーアやジャン・アルプの彫刻から影響を受け、1941年のPoet Sofaでは有機的なフォルムに浮遊感を与え、“座る彫刻”と称賛されました。伝統的な指物師資格を持たなかったため、職人ニールス・ヴォッダーとの緊密な協働で独自の構造と製作プロセスを確立し、既成概念を覆すデザインを次々と発表。優雅な緊張感をまとった作品群で、デンマーク家具を国際市場へ広める架け橋となりました。

ハンス・J・ウェグナー
Hans Jørgensen Wegner
ハンス・J・ウェグナーは14歳で木工修業を始め、17歳で指物師マイスター資格を取得した経験を活かし、“椅子の巨匠”と呼ばれます。1936~38年にコペンハーゲン美術工芸学校でデザインを学び、卒業後はアルネ・ヤコブセン事務所でオーフス市庁舎の家具設計に携わりました。1949年に発表されたCH24“Yチェア”は1950年以降も継続生産され、人間工学に基づく快適性と流麗なフォルムで世界中に愛用されています。日常の道具としての使い勝手と芸術性を高次元で融合させる哲学が支持され続けています。

イブ・コフォード・ラーセン
Ib Kofod-Larsen
イブ・コフォード・ラーセンは、もともと家具職人として最高位の成績で修業を終えた後、1948年に王立芸術アカデミーを卒業し、自身の工房を開設しました。ベーシックなチーク材やローズウッドを生かした家具を得意とし、1956年に発表したU-56「エリザベスチェア」は、英国女王エリザベス2世がペアで購入した逸話も残ります。そのほか、曲線美を追求した「ペンギンチェア」(1953)や「シールチェア」(1956)など、素材の質感を尊重しながら機能性と造形美を両立した作品を数多く生み出しました。ガラスやファブリック、家電のキャビネットなど、領域を超えたデザインも手掛け、当時のデザイン界に国際的評価をもたらしました

ボーエ・モーエンセン
Børge Mogensen
ボーエ・モーエンセンは、1934年に家具職人資格を取得後、1936年からコペンハーゲン芸術工芸学校でコーア・クリントに師事し、1942年には王立芸術アカデミーを卒業しました。1942年から1950年までデンマーク消費者協同組合(FDB)のデザインスタジオを率い、“庶民のデザイナー”として質の高い木製家具を手頃な価格で提供しました。1959年の「スパニッシュチェア」はオーク材とサドルレザーを組み合わせた堅牢で簡潔な構造が特長で、現在も多くの家庭で愛用されています。また、家庭内の道具や動線を調査し、収納ユニットを壁に組み込む発想など、実用性を科学的に検証したプロジェクトも展開しました。

新居 猛
NII Takeshi
新居 猛は、剣道具製造業を営む家業の三代目として育ち、戦後の職業補導所で木工技術を修得した後、1970年に帆布とスチールパイプを組み合わせた折り畳み椅子「ニーチェアエックス」を発表しました。カレーライスのように誰からも愛される椅子をコンセプトに、軽量かつ耐久性に優れ、梱包では空気だけを運ぶような無駄を省く設計が評価されました。経年劣化した部品は交換可能な仕様で、環境負荷を抑えながら長期間愛用できる点も革新的です。MoMAの永久コレクション入りを果たし、現在も国内外で根強い人気を誇ります。

吉村 順三
YOSHIMURA Junzo
吉村 順三は、東京美術学校(現・東京芸術大学)卒業後、1931年からアントニン・レーモンドの事務所で設計に携わり、その後1941年に自身の事務所を開設しました。1953年にMoMA「日本館」として建てられた松風荘(Shofuso)は、伝統とモダニズムを融合させた住空間を世界に紹介しました。1955年には前川國男、坂倉準三とともに国際交流拠点「国際文化会館」を設計し、日本建築学会賞を受賞。以降もハイファのチコティン日本美術館(1959)や奈良国立博物館新館(1972)など、木造住宅から大規模文化施設まで多彩な作品を手掛け、教授として後進育成にも貢献しました。
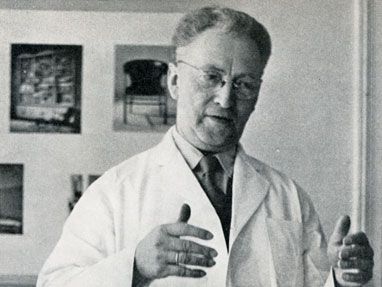
ヤコブ・ケア
Jacob Kjær
家具職人であった父の工房で修行後、家具職人としてベルリンやパリなど各地で修行をする。
スネーカーマスターとしてバルセロナの世界博他に作品を出展。多数の受賞経歴を持つ。
全体的にシンプルなデザインが多いが、ディテールなどの細部は驚くほど
考え尽くされているのがわかる。家具職人として材料や加工、構造や作業工程に至るまでこだわる、一流の職人であった。
※スネーカーマスター・・・最高の家具職人の称号

